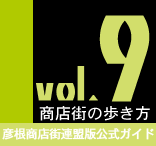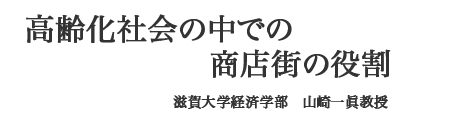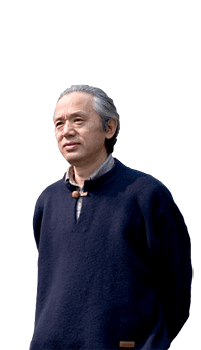
皆さん、2007年問題って知っていますか。戦後間もなく生まれた団塊の世代(昭和22年〜24年生まれ)が60歳の定年時期を迎え、現役引退を開始するのが2007年です。これによって、高齢化社会から高齢社会に変わり、種々の社会的問題が現れると予想されます。このような状況下で、商店街はどのような役割を果たすべきでしょうか?
1.中高年の生活の場としての役割
日本の都市は、いわゆる中心部と呼ばれる地区を中心にして同心円状に創られました。そのため中心部(商店街も含まれる)に近い地区ほど高齢者の割合が高く、遠ざかるに従って低くなっています。2007年以降この傾向が一段と強まり、商店街地区の高齢者比率はさらに高まり、高い比率のラインはその周辺に広がります。
つまり、商店街はまさに高齢者集積のまっ真ん中に位置するのです。当然、お客様は今よりも広い範囲にお住まいの高齢者の方が中心になるでしょう。なぜなら、高齢者は徐々に車依存の生活から徒歩・公共交通機関に変わっていくからです。
このことは近傍の豊富なサービス施設と相まって、商店街は中高年の生活の場になるということです。商店街はそれに備えねばなりません。生鮮3品を始めとした品揃えや御用聞き・宅配サービスなどは不可欠であり、高齢者の生きがいづくりやふれあいの場なども望ましく、さらに、デーサービスや診療所・病院の診療所予約なども備えていたいものです。勿論、施設はバリアフリーで、適所に木陰があり、ベンチや噴水なども欲しいところです。
2.中高年の自己実現をサポートする役割
日本の高齢者は、当面、金銭的・時間的・健康的に恵まれた方が多いと予想されます。その人たちは、旅行・レジャー、生涯学習やボランティアなどで自己実現を図る方向に進んでいます。
一般に中心商店街はその都市の歴史的遺産の近傍に位置し、これを少人数で見て歩くことは、旅行・レジャーはもとより、生涯学習の成果を確認する活動として今後一層活発になると予想されます。
商店街はそれ自身がその街特有の観光魅力であると同時に、来訪者に対してもてなしとサービスを提供する役割を担っています。商店街の関係者が街の歴史や文化の語り部でありたいし、宿泊・飲食・交通などの案内人でもありたいものです。
なお、生活の場としての役割と自己実現をサポートする役割は対立するものではなく、相互に相乗効果をもっています。
*高齢化社会と高齢社会 人口学では、高齢化率(全人口に占める65歳以上の人口の比率)が7%を超えた社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」とする。(「人口減少経済」の新しい公式 松谷明彦著 日本経済新聞社 より)