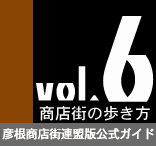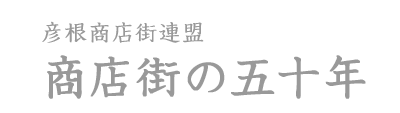嶋津慶子 夢京橋商店街
商店街連盟広報部長
50周年事業部会委員

藤野一雄 四番町スクエア
1960年頃より、市場街役員、商店街連盟役員を務める。

若林成幸 中央商店街
彦根商店街連盟副会長

小川太一郎
花しょうぶ通り商店街
前上恵美須商店街会長を30年間務める。
商店街連盟元副会長
現商店街連盟監事

北村久雄 夢京橋商店街
本町本栄会当時より商店街活動を続ける。現在、夢京橋商店街振興組合理事

野瀬正雄 橋本商店街
26歳より40年にわたり商店街連盟の活動に参加。昭和46年事業部副部長

松居 昇 銀座商店街
商店街連盟創立20周年記念誌部会長
彦根には伝統文化が無いから創ってきた。
司会(嶋津慶子さん) 今から50年前、昭和27年に彦根商店街連盟が誕生しましたが、本日は商店街連盟の草創期を覚えていらっしゃる方々にお集まりいただきました。半世紀前から現在、未来に至るお話をおうかがいしたいと思いますが、まず、50年前というのはどんな時代だったのでしょう…。
野瀬正雄さん 昭和25年は朝鮮動乱を契機に、日本の景気もよく、商売もどんどん盛んになっていった時代です。商品はあればあるだけ売れ、闇市みたいのもありましたから、「商売人は正しい商いをせなあかん」と、胸をはって正しい商売をしよう、一致団結させようと、彦根商店街連盟ができたことは画期的なことでした。滋賀県でも早い方ではなかったでしょうか。
藤野一雄さん 鋳物業界も戦後復興の需要でバルブ業界がすごかった。フル操業でしたしね。もの不足でつくれば売れる時代でもありました。それと、紡績工場。近江絹糸さんに六千人の女工さんがいたんですよ。休みになったら解放されてぱーっと町に出てきて買い物をする。そういう時代でした。
松居 昇さん 彦根商店街連盟設立当時の顔ぶれはそうそうたるもので優秀なメンバーが揃っていました。
近藤重蔵、野村善七、稲垣栄次郎、河原崎良三、野上周三、近藤一右衛門、西川庄五郎、山田茂…。明治生まれの智恵の固まりでしたね。
小川太一郎さん 銀座街の防災建築やお城のシールの発案も、その当時の中心的な存在はみな40代です。商店街連盟がはじまったのも若い英知が結集した結果だと思います。彦根の人は先取りの精神というか進んでいたんだなーと思います。
花しょうぶ通り商店街では、今、40代の若手が頑張っていてくれるわけですが、後に続く、若者が台頭してくれると上手に、世代交代ができるんですけれど…。
ただ、残念なことに、彦根には伝統的な文化がないんです。お城はありますけれど、いわゆる文化というものが育っていないわけです。滋賀県で伝統的なお祭りが残っていないのは彦根だけです。だから、過去に彦根の商人が小さな曳山をつくったりして、何かやろう、賑わいを創ろうと試みたのですが、新しく、つくったものは長続きしません。それでも、また次のことを考えて何とかやっていこうと、昭和30年に園遊会が始まったのも、彦根ばやしの総おどりも、そういう気持ちがあって、商店街が取り組んできたんです。
松居さん 川原町(現・花しょうぶ通り商店街・銀座商店街)の二・七の市は、夏の土曜夜市として受け継がれていますね。
北村久雄さん 実は、彦根にも本物の曳山が江戸時代にあったんです。本町にある京橋会館はもともとは山車蔵で、背が高くて吹き抜けがあり、2階が集会場で1階が倉庫になっていました。井伊直弼さんの暗殺で、武士だった人たちが彦根から離れたり、残った人たちも商人になり職人になってしまったわけです。勿論、明治維新後、彦根の復興に尽力された方々もいます。彦根の伝統や文化はあったのだけれども失われてしまった、或いは、途絶えてしまったと言う方が正しいでしょう。例えば、夏の七夕祭りの原点は本町なんです。慶山(けいざん)といって江戸時代の初めから親しまれた智福院というお寺があり、昭和30年頃だったと思いますが「慶山夏まつり」を復活して旧暦の七夕に笹飾りを始めたんです。お祭りになると本町では、屋根のついたお宮さんの入口に立っている「高張り提灯」を家々の軒先に立てたんです。今にして思えば、それだけで風情がありましたね。
野瀬さん 昔のそういうものが残っていればよかったんですが、確かに、彦根には伝統文化がないですね。木之本は地蔵さん、長浜は曳山、米原も曳山、それから近江八幡は左義長、大津も曳山……彦根の商店街としては「ゑびす講」が一番の文化ではないかと思っています。京都や大阪にいくと誓文払いといって、神様に正直に商売しますというのを誓うんですね。彦根ではそれを10月19日に行っていたのを、新暦になった明治6年からひと月のばして、11月20日にするようになりました。賑やかになったのは明治時代からです。
ゑびす講が商店街の一番の文化!!
藤野さん 今は農家の収穫は早くなって9月頃になりましたが、昔は11月20日というのはちょうど収穫の終わった時期だったのです。彦根のゑびす講というと電車で親元に帰ってきたり、三重県から大君ヶ畑を越えてやって来られたりしました。それに当時、湖東汽船があった時代で、長曽根に港がありました。商店街も元気で、湖西まで舟を出したりと…そこまでやっていたんです。船が西江州から11時頃にこちらに入ってくると、中央町がうわっと賑やかになって。皆、信玄袋をさげて…。とにかく、ゑびす講の時は大賑わいでした。
野瀬さん 子どもの頃、私はゑびす講は嫌だったんです。朝も6時頃から準備をして、本当は一ヶ月前から準備をするのですが、3食の食事も食べられず、町はにぎやかでも遊びに行けず、店の手伝いばかりで3日間、何をする暇もありません。それくらい賑わっていました。商店街連盟ができた当時なんかは、新聞折込なんかありませんし、木之本あたりまでキャラバンに出かました。
司会 昔…、覚えているんですけど、ミツワさんの中華そばがおいしかったですよね。
野瀬さん 田舎の人がゑびす講に来て、あそこで食べて帰るのがひとつのパターンでした。宮本寿太郎さんが戦前彦根で最初にラジオを購入し、店の前に大きなラッパー(拡声器)を付け流していました。
北村さん ヒノデさんはおたやんあめでした。
松居さん ちんどんやさんがでたり、宝恵かごがあったり、ゑびすさんのお面とか、彦根の人ならば皆それぞれ、懐かしい思い出があるのではないですか?
若林成幸さん 子どもながらに、ゑびす講はワクワクしました。私は中央町なんですが、中央町でももう一度ゑびす講を盛り上げようというので一生懸命やっています。銀座街も一生懸命取り組んでくださってるんですが、他の街があまり熱が入らないんですね。
野瀬さん それは多分、北野神社の十日ゑびすとバッティングしてしまうからじゃないでしょうか。恵比寿さんは働き者であちこちに出稼ぎに行かれます。11月に帰ってきて、1月10日に働きに出かけられる。十日ゑびすは出発の儀式だと聞いています。11月には土産を持って帰って来られるといって歓待したんですね。私が商店街連盟事業部の副部長をしたのが昭和58年です。何とか昔のゑびす講の賑わいを再現したいと思い、昔(戦前)のように船(琵琶湖汽船)をチャーターしたり飛行機でビラを撒くというような事をする元気はなかったのですが、「ゑびす講は、商店街の一番のイベント」であるという意気込みで、銀座・中央・登リ町・橋本の四商店街でギャル御輿というのをさせてもらいました。神輿3基に短大生100人程度来てもらって、ゑびす講3日間のうち2日朝10時から午後4時まで四商店街を2回まわりました。その後、ミス若あゆ(ミス彦根)にお願いし、ほいかご(芸者スタイル)も二基出しました。これが新聞なんかで取り上げていただいて、大阪の天神橋商店街に負けないくらい西日本で有名になりました。売上に貢献したかどうかはわかりませんが、商売というのはものを売るのではなく、お客様に喜んでいただくことだと思います。いまも私は思っているんですが、これだけものがありあまっているんですから、ものを売るという考えはだめだと。商売人というのはいつの時代も文化の伝統を発していなければなりません。
松居さん 彦根は戦争中戦火にもあっていませんし、江戸時代も井伊藩は一度も国替えがありませんでした…彦根は平穏無事なんです。それだけに活気が生まれない。彦根の人間は飽きっぽいのかもしれませんね。はじめたことを続けなくては意味がない。続けることがパワーであり力であると信じているのですが。市民がぐっと盛り上げたものを作らなくては、上からの押しつけとかは続かないわけです。ゑびす講でも商売人だけがやっているバーゲンセール、カーニバルじゃなくて全市の意気込みを感じるものにしたいですね。
北村さん 夏のねぶたから始まってずーっと徳島の阿波踊りまで、皮肉ったことをいえば悪政で民衆が圧迫されていた地域なんです。いわゆるガス抜きですね。3日間か4日間はもう無礼講であばれてガスを抜くと。彦根は裏をかえせば良い政治が行われていたのでしょう。